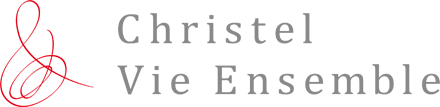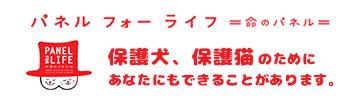小林史明衆議院議員(環境副大臣)を訪問 #飼い主に傷つけられた動物を守れる社会に

一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブル(以下、「当財団」とする。)は、2023年9月の動物愛護週間より「#飼い主に傷つけられた動物を守れる社会に」プロジェクトを開始し、署名活動を行っています。
去る12月11日 代表理事である滝川クリステルはどうぶつ弁護団理事長 細川敦史弁護士、平成国際大学 牧野高志教授とともに、小林史明衆議院議員(環境副大臣)を訪問。 当財団が次の動物愛護管理法の見直しにおいて求めている内容を説明し、意見交換を行いました。

左から細川敦史弁護士、小林史明衆議院議員(環境副大臣)、滝川クリステル、牧野高志教授
「このままではおかしい!このままではいけない!」と、我々に思いを託してくださった署名賛同者の皆様の思いに少しでも応えるべく、今後活動を続けてまいります。
【当財団が動物愛護管理法の見直しにおいて求める内容について】
特設サイトはこちら
https://christelfoundation.org/project/sos/petition/
署名サイトはこちら
【要約】
1)緊急一時保護 ~手遅れになる前に、“証拠”としてではない形で、虐待された動物が保護されるように~
虐待を受けている(疑いのある)動物を、行政は警察と連携して適切なタイミングで一時保護しなければならない
2)所有権の喪失 ~虐待を受けた動物が、虐待を繰り返す恐れのある飼い主のもとに帰らなくてすむように~
虐待の程度が酷い場合や飼養環境が改善されないなど一定の条件をみたした場合には、当該動物の所有権を飼い主から喪失させることを可能とする
3)行政による被虐動物の保管 ~虐待を受けた動物の居場所が確保できるように~
一時保護された動物は、原則として、行政が保管する(所有喪失後は、民間等とも連携の上、新しい飼い主探しを行う)
【詳細】
1)緊急一時保護
伴侶動物との共生において、飼い主(以下、「所有者」とする。)の責務は重大である。所有者は、動物の命と福祉のために、適切な飼養が求められる。その上で、所有者から虐待を受けた、または虐待を受けた疑いのある動物(以下、「被虐動物」とする。)の命と福祉を守るため、以下の通り、適切なタイミングでの一時保護を徹底する。
<積極的虐待(殴る蹴る、熱湯をかける等)の場合>
積極的虐待は、原則警察案件となるが、一刻の猶予も許されない状況においては、速やかな対応が必要となるため、警察だけでなく動物愛護管理センター等(以下、「行政」)の職員による一時保護も可能とする。
<消極的虐待(ネグレクト)の場合>
明確なガイドライン(期限・ゴール)を定めることとする。行政は、このガイドラインに沿って指導を行い、期限となっても、改善が見られない場合には、警察と連携し一時保護を行う。
一時保護をすべきかどうかの判断が困難な場合には、有識者グループ※1に見解を求める。
また、現状動物虐待に専門的な知見を持つ獣医師は限られるため、行政(動物愛護センター等)は、獣医師等職員に研修を受講させるなどし、虐待に対応ができる獣医師・職員の育成に取り組むことをあわせて明記する。
2)所有権の喪失
有罪判決の有無に関わらず、一時保護をした被虐動物にかかり、改善の余地がなく、飼養が困難であると調査および社会通念に則って判断※2された場合には、以下の通り、所有者から所有権を喪失させることを可能とする。
<所有者が有罪判決を受けた場合>
改めて立ち入り調査等を実施し、状況を確認する。改善の余地がなく動物の飼養が困難と判断※2された場合には、所有者から被虐動物の所有権を喪失させることを可能とする。
<所有者が不起訴等になった場合>
改めて立ち入り調査等を実施し、状況を確認する。改善の余地がなく動物の飼養が困難と判断※2された場合、所有者からの被虐動物の所有権を喪失させることを可能とする。
3)行政による被虐動物の保管
動物愛護管理センター等が、1)2)において保護された被虐動物の“保管”業務を行うことができるよう、動物愛護管理法 第37条の2を改正する。
保護された被虐動物を担当する地域の行政(動物愛護管理センター等)はもちろんのこと、他都市や他都道府県を含めた、全国の行政(動物愛護管理センター等)が一義的には保管義務を持つ。しかし、収容可能頭数を越えるおそれがあるなど、やむを得ない場合(特に多頭飼育崩壊等、一度に多数の動物の保護が必要となった場合)には、保管業務を獣医師会会員や民間の保護団体等に委託することを可能とする。
〈注記〉
※1 各行政は、有識者グループを作る。専門知識および社会通念に沿った判断が必要となるため、当グループには、行政獣医師および動物虐待に専門的な知識を有する外部獣医師(地域の獣医師会が推薦する獣医師や獣医系大学の専門家など)の2名以上の獣医師に加え、民間人や弁護士等が参加する。
※2 判断にあたっては、①環境改善に関する確認、②動物の体調、そして③所有者の経済状況および(心身の)健康状態を踏まえ、有識者グループ※1が社会通念に則って方針を策定。その上でその方針に沿って動物愛護管理センター長が最終的に判断する。なお、当該判断基準については別途ガイドライン(チェックリスト)を定めることとする